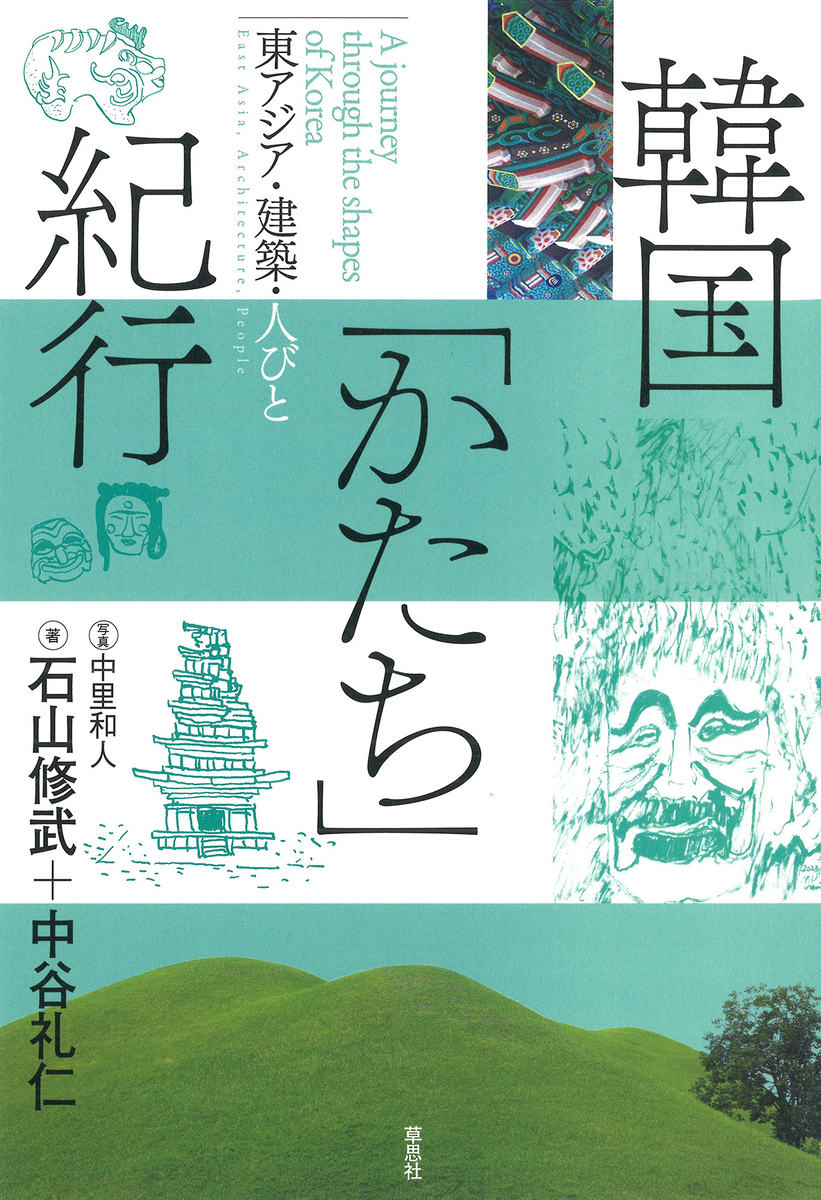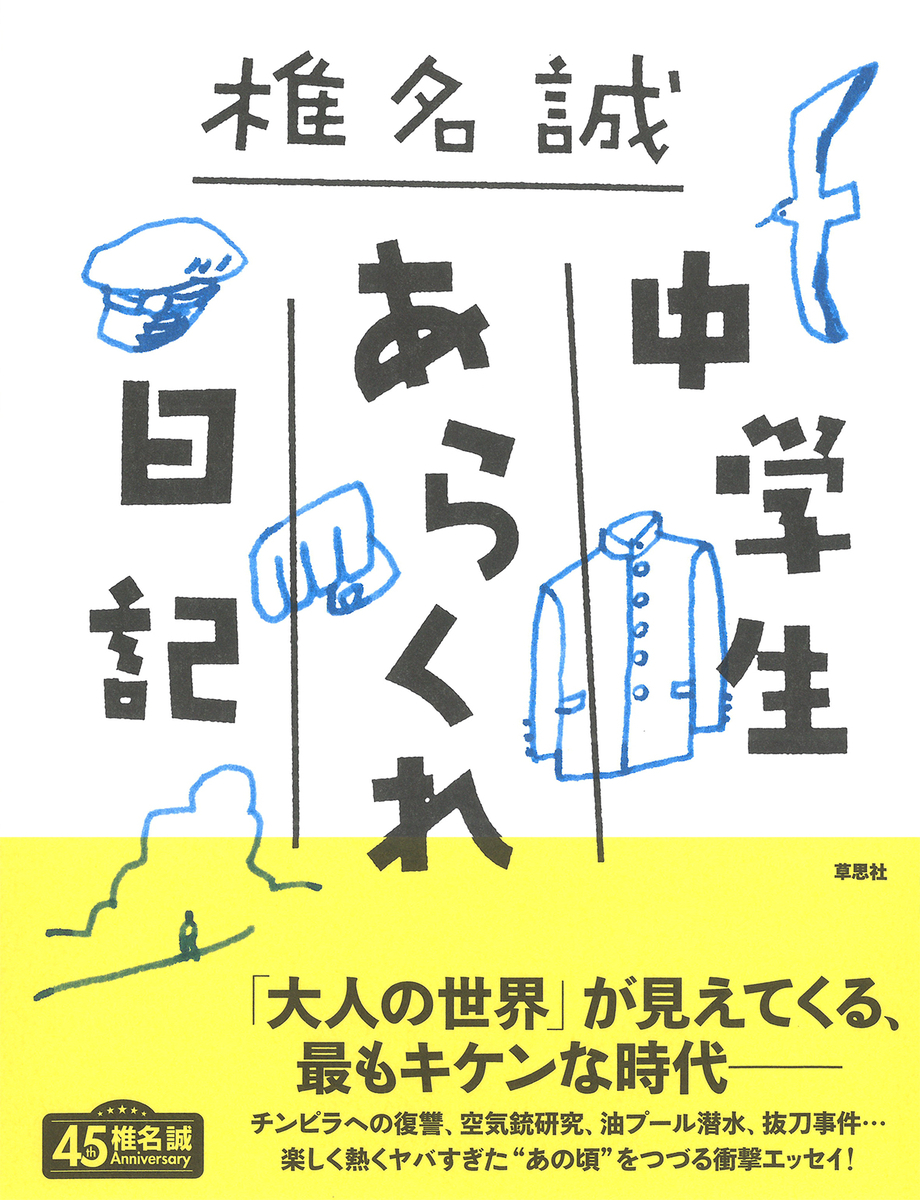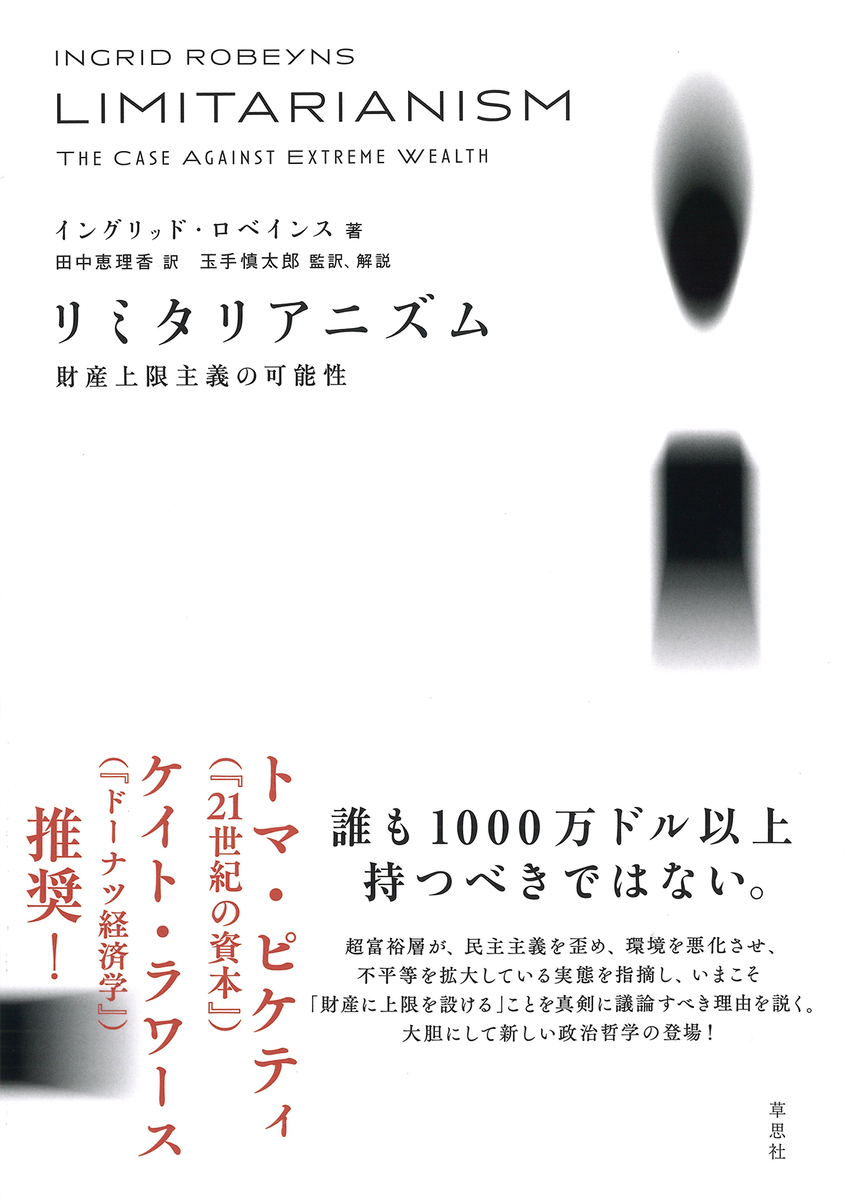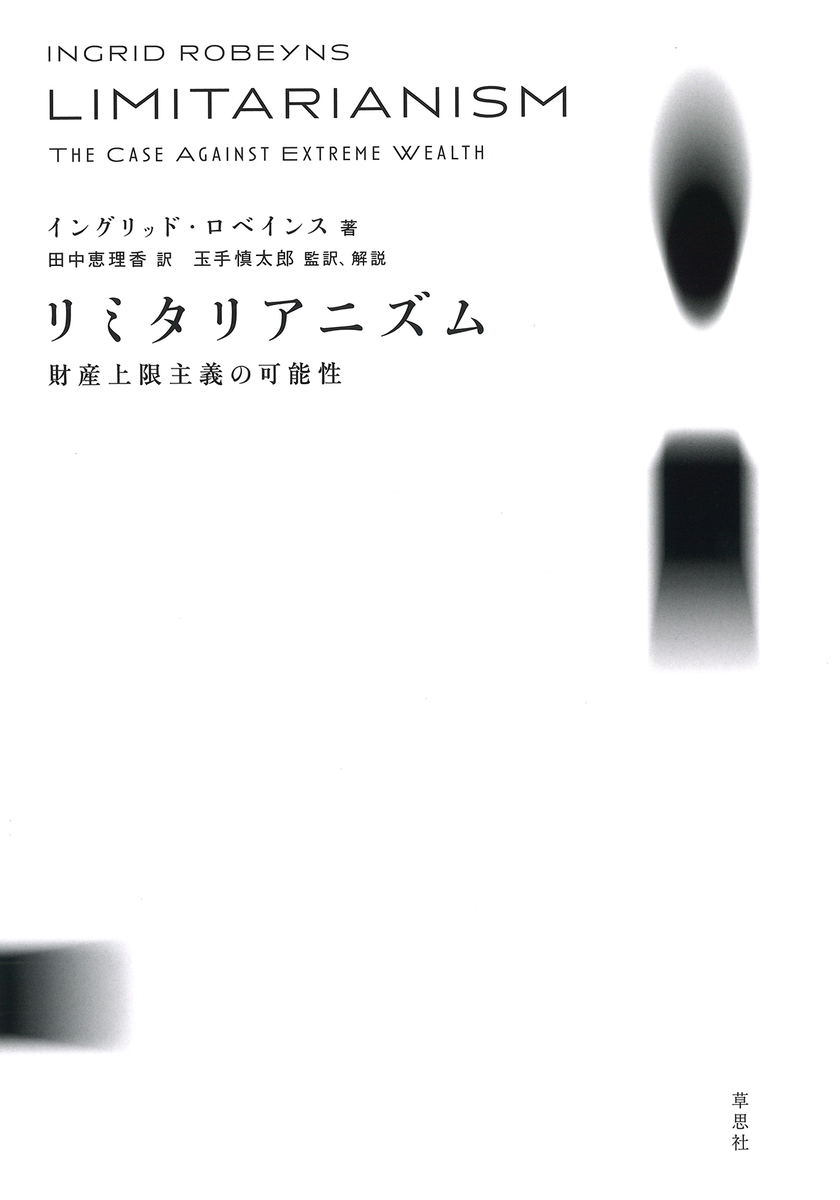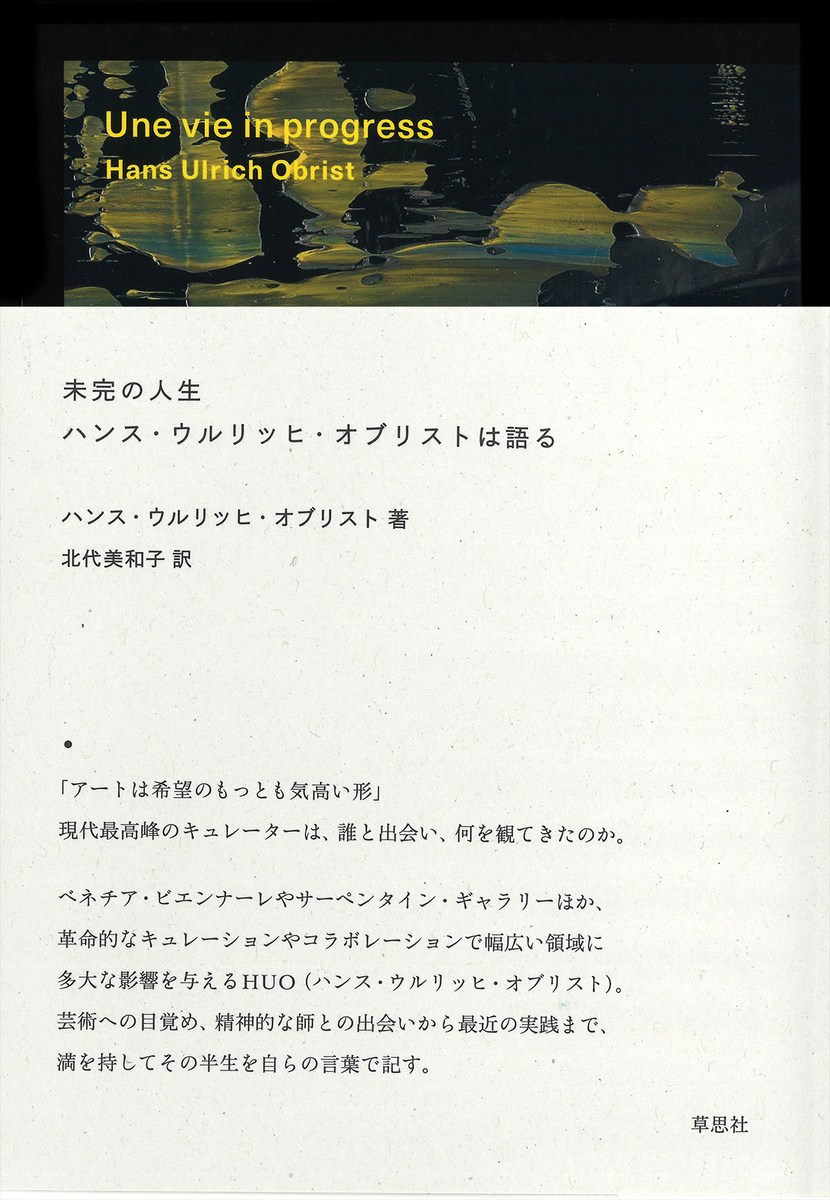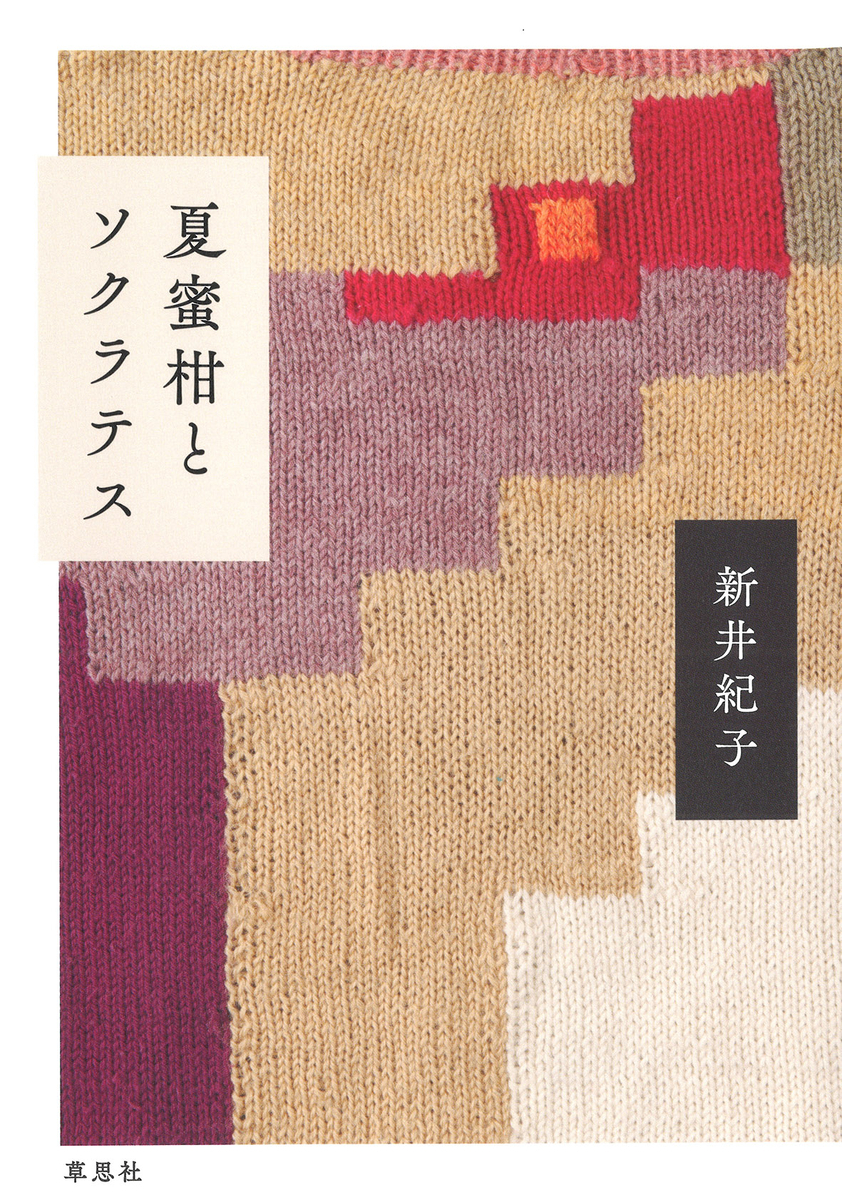偉人 大久保利通
――「正解なき時代」のリアリスト
真山知幸 著
大久保利通といえば、明治維新の立役者。倒幕を成功させて、日本を近代国家へ導いた人物です。正直に言うと、これまで私は「冷酷な独裁者」「西郷隆盛の陰に隠れた人」といったイメージを持っていました。
しかし本書では、そのイメージとはまったく違った人物像が見えてきます。
大久保は部下の意見に耳を傾け、礼を尽くし、筋を通すことを何よりも大切にしていた。強面のイメージとは裏腹に、実はとても人間味あふれる存在だった――そんな姿が次々に描かれ、ページをめくる手が止まりませんでした。
外交で理不尽な要求に屈せず、粘り強く交渉を重ねる姿も印象的。威張るのではなく、相手にきちんと向き合って日本を守ろうとする。その現実的で誠実な姿勢は、現代のリーダー像にも通じる気がします。
著者の真山知幸さんは『ざんねんな偉人伝』などでおなじみの偉人研究家。ユーモラスな切り口の著作から真面目な伝記まで、幅広く手がけていらっしゃいます。
今回はこれまでの作品とはひと味違い、一人の偉人にスポットを当てており、大久保利通を新しい目で見直せる、とても熱のこもった評伝になりました。
特に印象的だったのは、著者のこんな言葉です。
「組織を支えるのは人心であり、人心を納得させるのは当事者の公正な態度である」
忙しい中でも周囲に気を配り、礼を尽くしながら改革を進めた大久保。その姿を思うと、仕事で迷ったときに「大久保ならどうする?」と問いかけた著者の気持ちがよく分かる気がします。
歴史ファンはもちろん、日々の仕事や人間関係で悩む人にもヒントをくれる一冊です。
(担当/五十嵐)
目次
第1章 薩摩藩内の覚醒期(1830~1862年)
誕生 大久保や西郷を育てた薩摩藩の教育システム
不遇 父の処罰で世の理不尽さを味わった青年時代
接近 下級藩士の大久保が西郷に倣った出世の極意
同志 すれ違いは昔から? 大久保利通と西郷の本当の仲
説得 絶望して自殺を図った西郷に大久保がかけた胸刺す言葉
尻拭 大久保が青ざめた西郷の唐突な暴言
共通 大久保を抜擢した「島津久光」の意外な辣腕
突破 初対面の岩倉具視に意見を押し通す強引さ
強引 勅命を受け入れるべく老中を恫喝した身のほど知らず
抜擢 34歳で死に直面しながらも異例の出世
第2章 倒幕活動の奔走期(1862~1868年)
守勢 英国に戦争をふっかけた薩摩藩の「意外な戦略」
冷静 天皇の意向も無視 「好機も動かず」大久保の算段
奇策 薩摩藩が幕末に「スイカ売り決死隊」を作った真剣な訳
難敵 大久保を倒幕へ動かした「徳川慶喜」の仰天行動
念願 大久保が復帰に動いた「西郷隆盛」の意外な変身
転換 「変節の西郷」と「粘り腰の大久保」が目指す共和政治
交渉 大久保も徳川慶喜も活用 「心動く説得」の裏技とは
苦心 実は口約束? 歴史が動いた薩長同盟の意外な真実
強敵 家康の再来と倒幕派が評す「徳川慶喜」の意外な辣腕
困惑 倒幕派を追い詰めた」大政奉還」の意外な裏側
決行 「王政復古の大号令」で新政権樹立もかわす慶喜
誤算 慶喜の立ち回りのうまさで同情論が噴出する
挑発 西郷も弱気になった武力制圧をブレずに推進した
策略 「戊辰戦争」で西郷と大久保が3倍の敵を圧倒したワケ
第3章 近代国家の建設期(1868~1873年)
慎重 「鳥羽・伏見の戦い」勝利にも浮かれず
大胆 倒幕後に「大坂遷都」をぶち上げた納得の理由
変更 遷都でなく奠都「首都東京」誕生の歴史的事情
巧妙 反発必至の「版籍奉還」を首尾よく進める
厄介 明治維新で大久保利通を最も困らせた意外な藩
選択 西郷と大久保がリーダーに推薦した「木戸孝允」の実力
迷走 まとまらない明治政府に若手が立ち上がる
断行 戦争も覚悟した「廃藩置県」 不意打ちで実現
貪欲 内政を取り仕切る立場ながら2年も視察へ
沈黙 「岩倉使節団」での人生初の欧米視察で絶望する
洞察 時代に名を残す人物を正確に見極めていた
情熱 鉄血宰相ビスマルクの言葉に奮起する
不動 無謀な「征韓論」もスルーして休暇を取った
摩擦 西郷と大久保でも制御不能な男の正体
対決 「カミソリ」と称された明治政府きっての切れ者と対峙
寝技 大久保が「明治6年の政変」を仕かけて西郷は下野する
第4章 内政重視の宰相期(1873~1878年)
混沌 自らに権力を集中させた「孤独の権力者」
人事 思慮浅い男すら賢く使い「佐賀の乱」を誘発
非情 「佐賀の乱」の醜態を批判して江藤新平をさらし首に
決断 「征韓論反対」の大久保利通 「台湾には出兵」の背景
外交 理想を追わずにベストに近い選択を愚直に繰り返す
覚悟 かつての恩人「島津久光」を排除する
知略 「琉球併合」で清に密かに仕掛けた驚きの罠
対策 躍進の陰に大久保利通 「三菱」が海運で発展したワケ
頑固 官僚に「爺さん」と呼ばれた大久保の性格
改革 大久保利通が国力を育てる模範にした「意外な国」
不穏 地租改正への反発で大久保が恐れたこと
悲嘆 西郷の参戦に「そうであったか」と涙を流した
疑惑 西南戦争の裏にあった西郷隆盛「暗殺計画」の内実
無念 西郷と逢えずに「西南戦争」へと突入
着実 戦争の最中に「内国勧業博覧会」を開いて大成功
誤解 大久保利通「西郷の死をほくそ笑んだ」の噂
貫徹 維新の志を貫いて近代国家の礎を築いた
暗殺 「明治維新30年構想」を語って生涯を閉じる
著者紹介
真山知幸(まやま・ともゆき)
伝記作家、偉人研究家、名言収集家。1979年兵庫県生まれ。同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て、2020年から著述活動に専念。『偉人名言迷言事典』『逃げまくった文豪たち』『10分で世界が広がる15人の偉人のおはなし』『泣ける日本史』『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』など著作は60冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は計20万部を突破しベストセラーに。「調査月報」「朝日中高生新聞」「毎日小学生新聞」など各媒体で連載中。「東洋経済オンラインアワード2024」でロングランヒット賞を受賞。大学での講師活動やメディア出演を行い、YouTube「【偉人研究家】真山知幸チャンネル」でも発信を続ける。


Amazon:偉人 大久保利通 「正解なき時代」のリアリスト:真山知幸 著:本
楽天ブックス: 偉人 大久保利通 - 「正解なき時代」のリアリスト - 真山 知幸 - 9784794228062 : 本