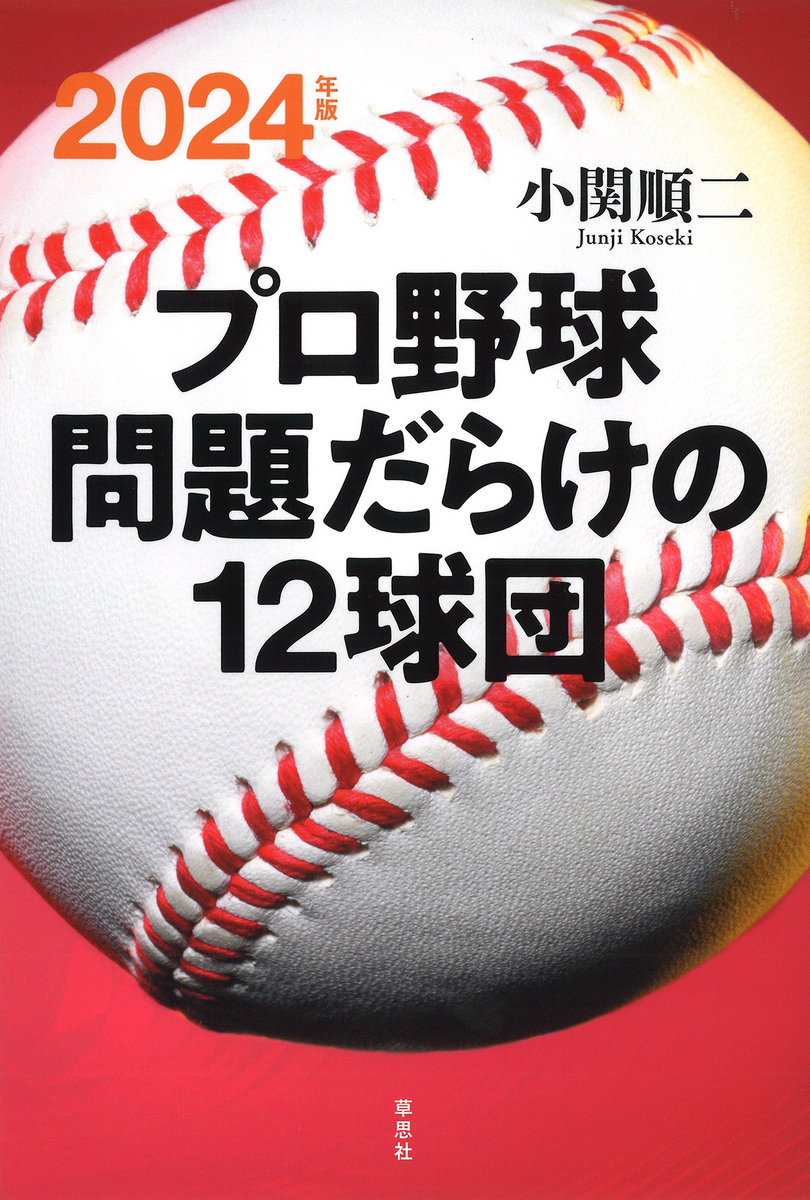挫折と覚醒の阪神ドラフト20年史
小関順二 著
長年「失敗ドラフト」を繰り返してきた阪神は、いつ、どのようにして甦ったのか?
昨シーズン、38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガースには、長く苦しい冬の時代がありました。即戦力として獲得したはずの投手はなかなか機能せず、スタメンには他球団から獲得したベテラン選手が目立つ――。そんなシーズンが長いこと続いていたのです。それが今やどうでしょう。スタメンにはドラフト上位指名の若手が並び、投打ともに12球団屈指のタレント集団へと変貌を遂げているのです。
阪神はいつ、どのようにして生まれ変わったのでしょうか。本書は「ドラフトがチームを変える」をモットーに2000年以降、12球団の全指名選手について年度版『プロ野球 問題だらけの12球団』でレビューし、同時に各球団のチーム編成についても詳細に観察してきた著者が、当時の自身の記述を振り返りつつ阪神のチーム作りの変遷をたどる一冊です。
ドラフトにおいては、即戦力(大学生・社会人)か将来性(高校生)重視か、投手か野手か、という究極の選択があるわけですが、著者はいずれにしても「ドラフト1位で将来の主軸を構成する」という方針をいかにブレずに貫けるかがチームの浮沈のカギを握る、と述べています。
そして、この点において注目に値するのが、監督就任にあたって「ドラフトですぐ使える便利屋のような選手を多く取る球団の体質が、生え抜きが育たない要因」と喝破した金本知憲氏による「改革」なのです。監督として大きな結果を残すことはできませんでしたが、阪神のドラフト指名の傾向を検証したとき金本監督の功績は明らかです。本書では、同氏の監督就任以前と以後でどんな変化が起こったか、そしてチーム力がどうなったかを検証していますが、そのあまりの違いに驚かれる方も多いかもしれません。
プロ野球チームという研ぎ澄まされた才能の持ち主が集う人間集団の編成において、「絶対的な正解」があるはずはありませんが、問題の根本に向き合って生まれ変わった阪神タイガースの軌跡は、やはり球史に残る歩みではないかと思えます。プロ野球をより深く楽しむために、ぜひお読みいただきたい一冊です。
(担当/碇)
【目次】
第1章 大転換――ドラフトでチームはここまで変わる
金本知憲の監督就任を境に激変した阪神ドラフト
「野手の1位指名」が意味するもの
スタメンに名を連ねる「ドラフト1位の野手」たち
大学生&社会人出身で形成された強力投手陣
高校卒投手の活躍が少ないのは阪神の伝統か
レギュラー野手に高校卒は何人いればいいのか
ドラフト1位投手が主力になれないのはなぜか
球界の流れに乗り遅れていた阪神とオリックス
ウエイトトレーニングがもたらした変化
常勝軍団を作るための土台
第2章 暗中模索からの起死回生――2000年からのチーム作りを再検証
チームを蝕む「伝統」の呪縛●2000年版の指摘●
「小技の2番タイプ」を上位指名する伝統/投手は線の細いスレンダー志向
「名将」野村克也の挫折●2001年版の指摘●
大物外様監督の明と暗/慢性的な攻撃力不足を招いた投手偏重ドラフト/「再生工場」は稼働せず、即戦力ドラフトも不発
「劇薬」投入●2002年版の指摘●
監督就任直後から圧倒的なスカウト力を発揮/野村と星野、監督として何が違ったのか/井川慶の本格化で急激な新旧交代が勃発
引き継がれない「強さ」●2003年版の指摘●
優勝監督・星野が遺した「負の遺産」/スタメンにドラフト上位指名選手が少なすぎる
分離ドラフトで失われた高校卒選手への「嗅覚」
「冒険心」なきチーム作り●2004年版の指摘●
新戦力の抜擢が上手い岡田新監督/主力と同ポジションの大物アマ選手を獲得する伝統/少なすぎる「生え抜き高校卒」投手
阪神フロントの問題点とは?●2005年版の指摘●
球界再編騒動の余波/進まない野手の世代交代/JFKの奮闘
岐路となった分離ドラフト●2006年版の指摘●
広がるセ・パの戦力差/セ・リーグの低迷は高校生ドラフトの失敗から始まっている/セの低迷を象徴する阪神のドラフト下手
ドラフトとファームを軽視してはいけない●2007年版の指摘●
「育成+抜擢」のサイクルが喪失/井川慶のメジャー流出で投手陣が弱体化
「急場しのぎ」の代償●2008年版の指摘●
なぜ高校生を上位指名すべきなのか?/歴史的な「V逸劇」を演じて監督交代へ
失われたチーム像●2009年版の指摘●
「ガス欠」を招いたビジョンなき編成/「育成する時間はない」という言い訳/思想が感じられないドラフト指名
「外人部隊」の役割とは?●2010年版の指摘●
生え抜き選手はスタメンに2人だけ/3年連続で「即戦力投手」を1位指名
俎上にのぼった「編成の問題」●2011年版の指摘●
坂井信也オーナーの「叱責」/統一球の登場で化けの皮が剝がれる/本塁打を打っているのは移籍選手と外国人
「守秘義務」を徹底すべし●2012年版の指摘●
「本当は高橋周平を獲りたかった」/外れ1位で指名するのは「無難な技巧派」タイプ
/33年ぶりの大物、藤浪晋太郎の獲得
藤浪という「起爆剤」●2013年版の指摘●
藤浪晋太郎賛歌/解消されないレギュラー野手の高齢化問題/ドラフトで3人の「成功選手」を獲得
育成か勝利か●2014年版の指摘●
高校生に投資すると言った楽天トップ/ドラフト1位、2位、4位で社会人の投手を指名
慢性化した貧打●2015年版の指摘●
鳥谷敬の後継者問題/「走攻守」という呪縛
ドラフト改革の始まり●2016年版の指摘●
金本知憲監督の改革がスタート/大器・藤浪晋太郎の挫折/金本の「厳しさ」、その功罪
チーム作りの「理想と現実」●2017年版の指摘●
「超変革」が意味していたもの/糸井嘉男獲得で露呈したフロントの不安/青柳晃洋の覚醒
新旧交代の狭間で●2018年版の指摘●
ドラフト改革の成果が見え始めた/23年の日本一を呼び込んだ「18年ドラフト」
「金本路線」の継承●2019年版の指摘●
「70点をめざす指名」への後退はありえない/建て直しも瓦解も「8年」が目安
将来を見据えた指名とは?●2020年版の指摘●
育成ドラフトに対する姿勢/驚異の「20年ドラフト組」にも高校生は1人だけ
オリックスの変化から何を学ぶか●2021年版の指摘●
新型コロナウイルスの余燼が燻る中での異例のシーズン/ドラフトでチームを変えるために必要な時間
スケール感を増すチーム●2022年版の指摘●
大山悠輔の成長から生まれた好循環/記録的連敗でもCS出場まで持っていく地力
充実した戦力だが、課題も●2023年版の指摘●
WBCの主力メンバーから見えてくる阪神の課題/ドラフトでチームを甦らせた阪神
第3章 未来の担い手
2023年のドラフト1位指名から見えてくること
独立リーグで野球をするメリット
2人の高校卒遊撃手への期待
下位指名「即戦力」投手の特徴
育成指名2選手のポテンシャル
受け継がれる「金本メソッド」
阪神ドラフト〈成功選手〉年表
著者紹介
小関順二(こせき・じゅんじ)
スポーツライター。1952年神奈川県生まれ。日本大学芸術学部文芸学科卒業。プロ野球のドラフト(新人補強)戦略の重要性に初めて着目し、野球メディアに「ドラフト」というカテゴリーを確立した。2000年より年度版として刊行している『プロ野球 問題だらけの12球団』シリーズのほか、『プロ野球 問題だらけの選手選び─あの有名選手の入団前・入団後』『甲子園怪物列伝』『「野球」の誕生 球場・球跡でたどる日本野球の歴史』(いずれも草思社)、『ドラフト未来予想図』(文藝春秋)、『野球力 ストップウォッチで判る「伸びる人材」』(講談社+α新書)、『間違いだらけのセ・リーグ野球』(廣済堂新書)、『大谷翔平 奇跡の二刀流がくれたもの』『大谷翔平 日本の野球を変えた二刀流』(いずれも廣済堂出版)など著書多数。CSテレビ局スカイ・A sports+が中継するドラフト会議の解説を1999~2021年まで務める。同会議の中継は20年度の衛星放送協会オリジナル番組アワード「番組部門中継」の最優秀賞を受賞。15年4~7月に、旧新橋停車場 鉄道歴史展示室で行われ好評を博した「野球と鉄道」展の監修を務める。